|
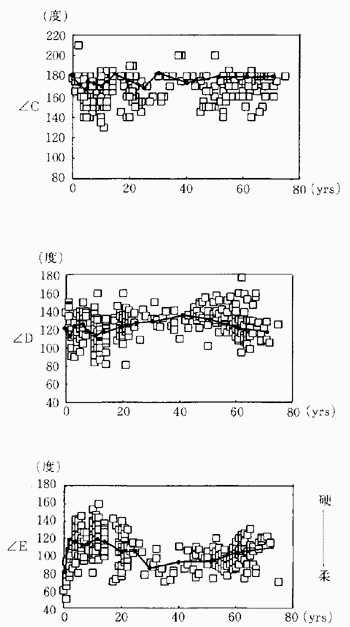
図13 屈曲角、∠C、∠D、∠Eの年齢による変化。(実線は各年代の平均を結んだもの)。
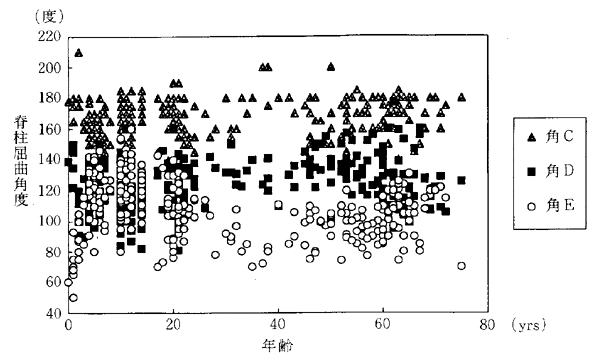
図14 屈曲角、∠C、∠D、∠Eの年齢による変化。
曲パターン『B型』の出現とあわせ、この時期の屈曲度減少は、矢部18)も指摘するように、幼児期の姿勢制御能の一時的な退行が影響するとも考えられる。本論の対象児の場合も、坐位では可能な屈曲度を立位でとれない事例が多かった。学童期から思春期にかけては、他の年齢に比べ『角E』の屈曲度が減少し、「角C』とくに思春期で『角D』が増加する。『単一角度法f.I』でも、この期の平均値は下がり、(6歳=-17.6度、10歳=-10.1度、11歳=−17.4度、12歳=−15.6度)個人差も大きい。10〜12歳は形態の思春期スパートの時期にあたり、急激な身長、とくに下肢比の増大や、形態と機能のバランス変化が影響すると考えられる。たとえば、春日ら3,4)はラットを用い、筋長が増加する時期に、一時的に筋力が低下することをたしかめている。また、森下11)も思春期に一過性の調整力のみだれがあると報告した。しかし、思春期の形態と機能の統計的報告では、相関の有り・無し両論があり1)、思春期スパートの個人差が結果に影響していると思われる。幼児期から思春期にかけて、頸椎部から胸・腰椎部の屈曲度の高い事例の出現率が増す。 40歳以降についてみると、『角C』には変化がなく、『角D』はなだらかに上昇、『角E』は低下するが変化率は少ない。多くの報告では、成長期には年齢とともに屈曲度が増し、20歳をピークに、その後低下してゆくという9,16)。またSermeev13)は4500人にわたる子どもと成人の股関節の可動
前ページ 目次へ 次ページ
|